シンクロニシティ と言う言葉を 聞いたことがあるだろうか?
オカルト的な、占いや神秘的な世界のことだと誤解している人も多いが、違う。
心理学者のユングが提唱する「科学的事象のこと」だ。
身近に起こるシンクロニシティの具体的な事例
ふと昔の友人のことを思い出し「最近、どうしてるんだろう」と思っていたら、その友達と街でバッタリ会って驚いた、という経験はないだろうか?
あるいは、近頃会っていなかった人のことを思い出して、なんとなく連絡したら「今、ちょうど君のことを考えてたよ!」と相手に驚かれた、なんていうこともある。
その場にいないはずの人の悪口を言っていたら、急にその人が現れてびっくりしたというケースも少なくない。

他にも、
「ふと見た時計に同じ数字が並んでいた 1111 2222 のような」
「時代劇でよくある 鼻緒が切れた、不吉なことが起こる」
「人からもらったものが壊れた。その人の身に危険が・・」
などなど・・・
虫の知らせや第六感のように、
「理屈では説明できない感覚によって何かを察知したり、予感が的中する」
シンクロニシティ
心理学者のユングはシンクロニシティが起こる理由を「集合的無意識によるもの」とした。
集合的無意識とは、個人の心理より心の深層にある「無意識の層」のことで、普段は意識できない領域のこと。
「表面上の因果関係はなくても、無意識の層においては繋がりがあるため、シンクロニシティが起きる」とユングは提唱したのだ。
もっと簡単に言うと
人間は1人ひとり個別に生きていても、心の奥底で繋がっている。その「繋がっている人間の波長」が共鳴した時に起こるのが【シンクロニシティ】
ということだろう。

「ふと」「たまたま」「なぜかそう感じた」というような、論理的に説明がつかない感覚は【シンクロニシティ】である可能性が高い。
以前紹介した セレンディピティ(serendipity)と似たような言葉
だが、ちょっと違う。
セレンディピティ とは、素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見すること。また、何かを探しているときに、探しているものとは別の価値があるものを偶然見つけること。平たく言うと、ふとした偶然をきっかけに、幸運をつかみ取ることである。
シンクロニシティ と、セレンディピティ との違いは、
セレンディピティ 一見関係ないものが自分の幸運につながっている。という概念。
シンクロニシティ 人間は個人個人は独立しているけれども、心の奥底ではつながっており、その繋がっている部分が「共鳴しあって」引き寄せのようなことが起こったり、人間の野生の本能「危機意識」や「第六感」のような鋭い感覚が現れる。
共鳴が起こるか、起きていないかの違いと言える。
しかし、どちらも 未来に影響を与え、受け止め方次第で幸運にも不運にもなる、という部分は共通する。
心の奥底ではつながっている というのは、胎児と母親を例に説明できる。
胎児は母親の一部である。臍の緒が切れるまでは「母の内臓の一部のようなもの」だ。栄養も、母親から吸収する。
しかし臍の緒が切れた瞬間に「個人として誕生し、1人の人間として生きてゆく」
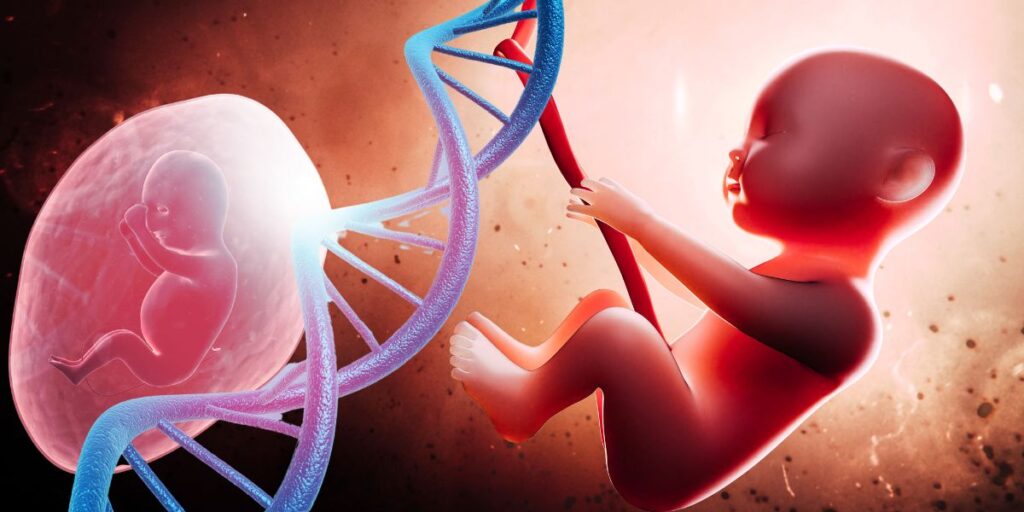
であるならば、個人は「人間の歴史の中で、1つの細胞」に過ぎず、死ねばまた「人間の歴史という大きなくくりの中に戻っていく存在」であり、生きているうちは「小型探査機のように世の中の様々を観察し研究し、サンプルを持ち帰り 成功失敗という経験値も母体に持ち帰る」
のかも知れないな、と考えたりする。
いずれにしても、共鳴が起こって シンクロニシティ を経験したり セレンディピティ によって全く関係ない方向から幸せになった、という経験は誰にでもあるだろう。
非科学的なように見えて、とっても重要な あなたに関係ある事象なのだ。

実は今回の物語の前後、ボクは頻繁に シンクロニシティ や セレンディピティ を経験している。当時はまったく気がついていないけれど。もっと上手く、それらを使いこなせれば良かったな、と思う。
なぜなら、それらが頻繁に起こるということは、次のステップに進む合図 だからだ。
あなたは ボクのストーリーから、それらを読み解き、もっと上手くシンクロニシティ や セレンディピティ を活用できるようになると思う。あなたの幸運を祈って、今回の物語を配信する。
具体的なストーリーで考えるヒントをつかもう。
ドキュメンタル STORY で人生をリセット!
〜机上の空論じゃ現状を変えられない。実例からヒントを得よう〜
ボクについては プロフィール を見てね

SONG-40 ダイアモンドの原石
劇団の女の子
この時のバンドはギターもドラマーも、そこそこのテクニックがあるし、音楽的知識もあるから信頼できる。音楽修行中のボクが音楽的に成長できる環境だった。
彼らには音楽について、いろいろ教えてもらっていた。そこはすごく感謝している。
しかし、悲しいかな、バンド的には つまんない。グループとしての魅力がないんだ。
「このバンドじゃ天下は獲れない」
それが本能的にわかった。

一方、劇団の女の子達は、個性的で前向きで楽しいんだけど、残念ながら技術がない。それ以前に役者だから楽器も弾けない。技術と魅力、両方が揃わなければ、ボクの夢の実現はない。
「あいつらが役者じゃなくミュージシャンだったらなぁ」
と何度も考えたが、しょせんかなわぬ夢だ。
「矛盾」と「葛藤」を抱え、ボクは2つのグループを行ったり来たりしていた。

その女の子達との芝居の公演が終わって。喫茶店かどっかで話をしたのかな?
「あたしたち、今後もカズさんとやりたいんです。駄目ですか?」
駄目ですかって言われてもねぇ。
ボクはもう芝居じゃなくて「バンド」。バンドがやりたい訳じゃない? そっちへ気持ちが向いちゃってる。
そりゃあ コイツらといると楽しいよ。常に先へ、先へ。進んでいこうっていう前向きなエネルギーがある。
バンドマンはもっとクールだからね。 “ハス”に構えてハッキリとした態度を示さないんだ。
「お前らは、今後 芝居を続けてどうなろうとしている訳?」
「どうって・・・・? 楽しいから いいじゃないですか」
「楽しいだけじゃ続けて行ける訳ないだろう? オレはそうやって時間を無駄にしてきたんだ。続けるためには、もっと“展望”がなけりゃ駄目だよ。例えば、オレがやりたい音楽の世界には、オーディションというものがある。実力をつけて、そうオーディションに受かれば プロとしての道も開けてくる。ずっと続けたいってことは、プロになるってことだ。アマチュアのままじゃ・・・そのうち仕事が忙しくなって毎日の雑務に追われ、自然にやめなきゃならない日が来る」

「・・・・・」
「うーん。だからカズさんが力貸してくださいよ。どうやったら劇団でメジャーになれるんですか?」
「劇団でって・・・ウーン。そうだなぁ。もし劇団が有名になるとしたら、“露出”だろうな」
「えっ? 露出って・・・裸になること?」
女の子たちは一斉に引いた。そして「やらしい世界に連れていく」ボクを避難するような目で 見た。突然 スケコマシ にされたボクは慌てて、
「ち・・違うよ。もっと人前に出ること。人に見て貰う機会を増やすってことだよ。アホ」
と言うと、張り詰めていた緊張の糸を一気に解いた彼女たちは「なぁーんだ」という顔をして お互いを見て頷き合い、
「アー、びっくりした」
と言った。

「こっちがびっくりしたわ、ふざけるな!」
急に変態扱いされたことを抗議したボクを無視するように連中の1人が、
「でも どうやったら人前に・・・」
すがるような目でボクを見たから「やれやれ」という気分で説明した。
「例えば。ミスター スリムの場合だと、自分たちの専用スペースを持って、毎日 毎日芝居を打つって意味を込めて、DAY BY DAY―――D・DAYシアターってものを作った。小さな小屋だけど、毎日やることによって芝居が練れてくる。クウォリティが上がるんだ。人に見られるってことで、育てられていく。そうすれば それを見た客が満足して、家に帰って家族とか友人に話す。次の日もやっているから、じゃあ見にいってみようかって。どんどん口コミが効いてくるんだ」
「なるほど。それいいじゃないですか。持ちましょうよ。自分たちの専用小屋」
「馬鹿。いくらかかると思ってんだよ」
「いくらですか?」
「莫大な金額だよ、無理!」
「えーー」
彼女たちは不満げに椅子にそり返り、伸びをした。

一方、バンドはベースが居ない状態が続いていた。
「この現状を打破するためにも、ベースが必要だよ。誰か知らない?本物のベースじゃなくてもいいんだ。キーボードを弾く奴なら、“シンセベース”って手もある」
トミノスケがボク達に言った。
その時、ひらめいたんだ。
「そういえば劇団の女の子の中に、昔ピアノをやってたっていうメンバーがいたな」
「えっ、本当? じゃあ その子、連れてきてよ」
「でもアイツら、芝居しか興味ないぜ。バンドなんか・・・やるかな?」
「とにかく一度、話してみてよ」
そのメンバーは、ヤスコって奴だった。素直で一本気なんだけど、自己主張が強くて 我がままな所もある。若いからね、しょうがない。
皆からも、「お姫さま」って言われてたんだ。そのぐらい気性が激しいから。

声を掛けると、
「あっ、あたし それ出来ますよ」
すんなりOKした。他のメンバーから自分だけが選ばれたっていうプライドもあって、
「あたし、カズさんのバンドでキーボード弾くことになっちゃった」
って自慢してんの。これは ちょっとした騒ぎになった。
「えっ、ズルーい。ヤスコばっかり。何だよォ。抜けがけ」
「いやいや。他のメンバーもそのうち、劇団でバンド作って皆で音楽やろうよ」
その場を収めるためにそう言ったの。そしたら、「レイ」っていうメンバーが勘違いしちゃった。
「えっ? あたしたちもバンドに入れて貰えるんですか? じゃあ ヤスコが行く時、あたしも見学に行こーっと」
そうじゃないって! と言う雰囲気でもなかったし。まあ いいやって。ほっといた。

ヤスコがバンドの練習に参加して。
最初 シンセでシンセベース弾かせてたんだけど、ぷーっと ふくれちゃって。
「面白くなーい。あたしずっとピアノやってたんです。こんな単純な シンセなんて。しかも低い方で、ボッ、ボッ、ボッ、なんて」
それを聞いていたレイが、
「あっ、だったら私 シンベ(シンセ・ベース)やりますよ。ヤスコはキーボーディストに専念すればいいじゃない?」
「やったこと あるのかよ」
「ああ・・・昔、教職取るのにピアノも弾けなきゃならないからって、練習したんですよ。うまくないけど」
レイは教師の資格、持ってるんだ。親も教師で。おかたい家庭なの。で、彼女は今、やわらかい世界にいると。
「ブッ、ブッ、ブッ、ブッ」
飽きもせず、単調なシンセベースを レイは弾くようになった。
ベーシスト?も決まり、勝手に「キーボーディストとして就任した」ヤスコも加わり。これでバンドメンバーが揃った訳だ。

ところがそれを聞きつけた他のメンバー達は、
「ズルイ。2人とも。知らないうちにメンバーになっちゃって」
「そうだよ。あたしたちも見学に行く」
って、次の練習から スタジオに現れて。虎視眈々と狙ってるんだ。自分たちのパート、入り込む隙間はないかって。目がギラギラしてて。獲物を狙う野獣みたいになっちゃって。
練習しづらいよ。


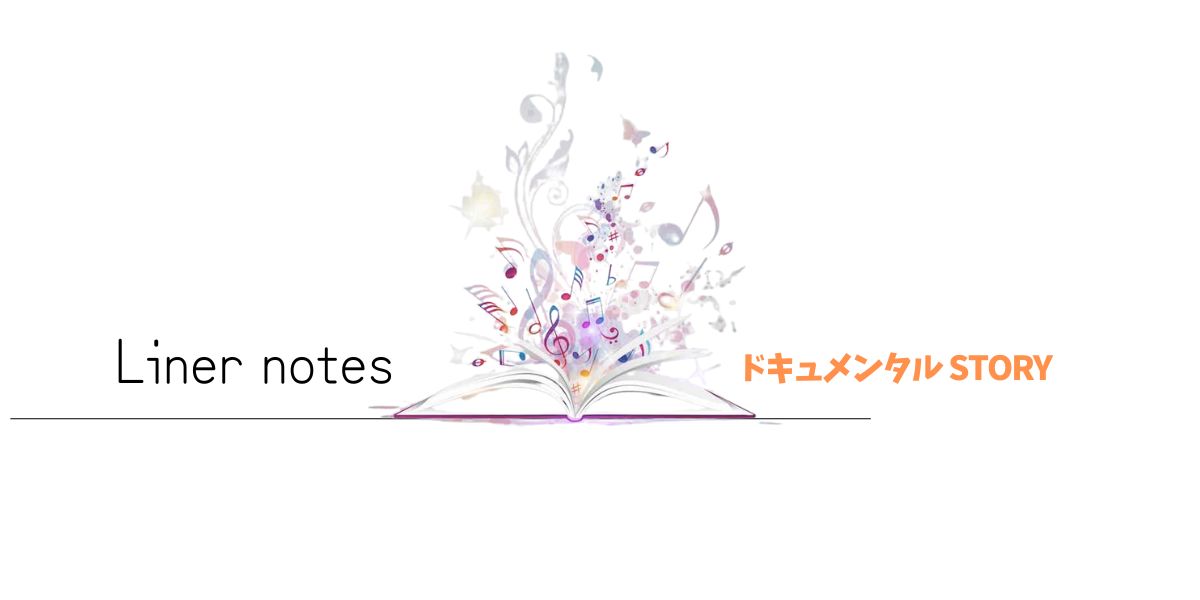
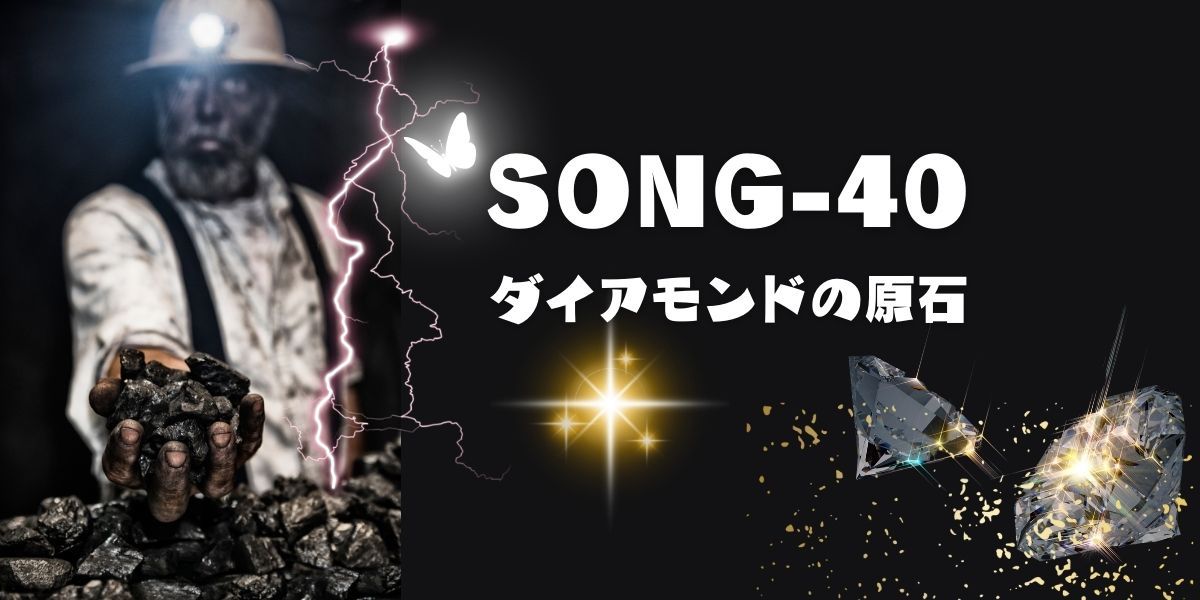
コメント